真和総合法律事務所

| 事務所名 | 真和総合法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5385-2337 |
| 所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-14 日本橋加藤ビルディング4階 |
| 担当弁護士名 | 片桐 武(かたぎり たけし) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
第一東京弁護士会 No.36525 |

交通事故後の不安に寄り添う──経験豊富な弁護士がサポートします
当職はこれまで、交通事故に関する損害賠償事件を多数取り扱ってまいりました。2016年度からは「日弁連交通事故相談センター」東京支部委員として活動し、2017年度からは実務家に広く参照されている『民事交通損害賠償額算定基準(赤い本)』の編集にも携わっております。
交通事故に遭うと、治療や仕事の調整、生活への支障など、日常が一変します。さらに保険会社とのやり取りや、過失割合・休業損害といった複雑な問題に直面し、精神的にも大きな負担となります。
事故の内容や保険会社の説明に納得がいかないと感じたときは、ぜひ弁護士にご相談ください。長年の経験をもとに、適切なアドバイスと対応で、皆さまの不安を軽減できるよう尽力いたします。
| 定休日 | 祝 | ||||||||
| 相談料 | 初回相談無料 | ||||||||
| 最寄駅 | 地下鉄「日本橋駅」B0・B5出口より徒歩約1分 JR東京駅「八重洲」北口・日本橋口より徒歩約7分 |
||||||||
| 対応エリア | 東京都 | ||||||||
| 電話受付時間 | 平日 10:00~20:00 土日 10:00~17:00 |
||||||||
| 着手金 | 無料 | ||||||||
| 報酬金 |
|
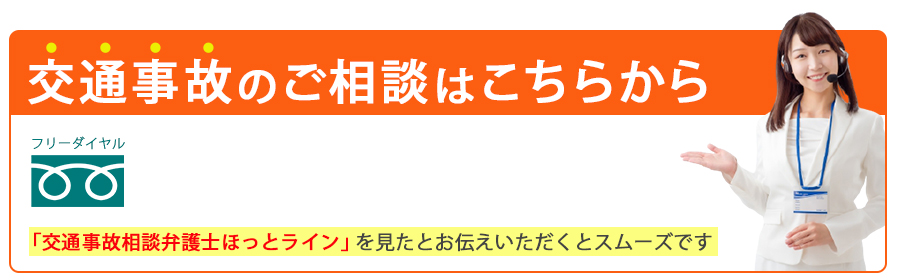
【対応分野】真和総合法律事務所
過失割合はどう決まる?──納得できないときは弁護士へ相談を
交通事故に遭った後、納得がいかない事例として多く挙げられるのが「過失割合」です。この割合が決まると、損害賠償額から過失分が差し引かれるため、損害が大きくても賠償額が減ってしまうことがあります。
過失割合は、事故の状況や過去の裁判例をもとに、保険会社同士の話し合いで決定されるのが一般的です。警察の実況見分調書やドライブレコーダーの映像、目撃証言などの客観的証拠も参考にされます。
一度決まった割合は、後から覆すのが難しく、「なぜ自分に過失があるのか納得できない」といった声も少なくありません。そのため、過失割合に疑問がある場合は、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。適正な判断と交渉により、納得のいく解決につながる可能性があります。
【事例紹介】過失割合30%→5%へ──直進車の正当性を主張し適正評価へ
当職は、交通事故に関する多数の解決実績があり、過去の判例や事故態様に応じた過失割合の立証方法にも精通しております。ある事例では、依頼者側の過失割合が30%と提示されていたものの、最終的には5%まで削減され、相手方の過失割合は95%に修正されました。
この事案は、依頼者が直進車、相手方が進路変更車という構図で、道路交通法でも不意不急の進路変更は規制されています。基本割合は3:7がベースとされるものの、「ぶつけられた」という依頼者の感覚と提示された過失割合に大きな乖離がありました。
そこで、衝突箇所や状況を精査し、過去の裁判例をもとに依頼者の正当性を主張。結果として、適正な評価を受ける形で解決に至りました。過失割合に疑問がある場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
年間70件超の交通事故対応──経験に基づく安心のリーガルサポート
当職は交通事故分野に精通し、現在も年間70~80件を超える交通事故事件の解決実績を積み重ねております。弁護士を対象とした研修講師も務めており、交通事故に関する多様なトラブルやそのパターンに豊富な経験を有していることが強みです。
被害者の方の立場や状況、ご要望に応じて、的確かつ丁寧な対応を心がけております。これまでの経験をもとに、今後の見通しや解決までにかかる時間、費用、必要な手続きなどについても分かりやすくご案内いたします。
交通事故に関する不安や疑問を抱えている方は、どうぞ安心してご相談ください。専門的な知識と実績をもとに、納得のいく解決を目指してサポートいたします。
後遺障害の等級認定が損害賠償額を左右します
交通事故によるけがで治療を受けても、後遺障害が残ってしまうことがあります。その際、どの程度の障害が残っているかを判断する「等級認定」と、収入や労働能力の喪失による「逸失利益」などが、損害賠償額に大きく影響します。
後遺障害の等級は、症状や身体の可動域などに応じて1級から14級までに分類されます。この等級が認定されることで初めて、後遺障害に関する「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」を正式に請求することが可能になります。
適正な等級認定を受けることは、将来の生活保障にもつながる重要なステップです。後遺障害に関する不安や疑問がある場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
後遺障害診断書の精度が等級を左右します──医師面談・意見書で適正評価へ
後遺症が日常生活や業務にどのような支障を与えているか、痛みの頻度や程度はどのくらい残っているか──これらは後遺障害の等級認定において非常に重要な要素です。当職は必要に応じて依頼者と医師面談に同行し、後遺障害診断書の記載内容を充実・適正化するよう努めています。
また、診断書には事故情報を添付することも可能です。車両の破損状況やドライブレコーダーの記録、修理内容などを弁護士の意見書として整理し、医療機関や外部機関での追加検査結果を所見として添付することで、事故の実態と被害の深刻さを正確に伝えます。
後遺症の症状に応じて、どのような資料が必要かを熟知していることも、当職の強みです。適正な等級認定を得るために、ぜひご相談ください。
後遺障害の認定は慎重に──異議申立ても視野に適正な評価を
後遺障害の認定では「非該当」とされるケースもあり、特に画像所見だけでは判断が難しい「むち打ち」などの事例では、14級相当の認定すら得られないこともあります。
そのため、保険会社任せの「事前認定」ではなく、自ら資料を整えて申請する「被害者請求」による手続きが重要です。
納得のいかない等級が出た場合には「異議申立て」を行い、追加検査や画像診断サービスの活用により、所見の補強を図ります。
当職はこれまで、死亡事案や後遺障害1級の重度事案も多数対応しており、あるケースでは賠償額が1億円を超えました。これは適正な請求と、正確な障害認定がなされた結果です。交通事故は人生を左右する重大な出来事です。培ってきた経験とノウハウを活かし、納得のいく解決を目指してまいります。どうぞ安心してご相談ください。
逸失利益の正確な請求には専門的な判断が不可欠です
後遺障害の等級認定が確定した後は、収入面に関わる「逸失利益」の請求が重要な段階となります。この逸失利益は、事故前の収入を基にした「基礎収入」や、労働能力の喪失率をもとに算定されますが、その評価には裁判例や実務上の知見が不可欠です。
たとえば、脊柱の圧迫骨折による変形障害で等級が認定された場合でも、労働能力の喪失率については判断が分かれ、想定よりも低く評価されることもあります。同じ等級・収入であっても、主張の仕方によって賠償額に大きな差が生じるのが実情です。
当職は、長年の経験と蓄積した知識をもとに、適正な評価を得るための主張・立証を丁寧に行い、依頼者の正当な利益を確保するよう尽力しています。逸失利益の請求に不安がある方は、ぜひご相談ください。
交通事故の相談は早めが肝心──治療中でも示談後でも対応可能です
交通事故の法律相談は、治療中の段階でも、保険会社から示談額が提示された後でも、いつでも可能です。ただし、治療の段階から弁護士が関与することで、保険会社との交渉窓口となり、適切な損害賠償を得るためのサポートが可能になります。
交通事故の件数は減少傾向にあるとはいえ、令和2年には全国で30万件以上の事故が発生しています(内閣府「令和3年版交通安全白書」より)。突然の事故により、治療・仕事・生活のすべてに負担が生じてしまう方も少なくありません。
弁護士に依頼することで、交渉や連絡の窓口を担い、依頼者様は治療や仕事復帰に専念することができます。一つひとつのサポートが不安の軽減につながりますので、事故後はできるだけ早い段階で専門家への相談をおすすめします。
アクセス
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
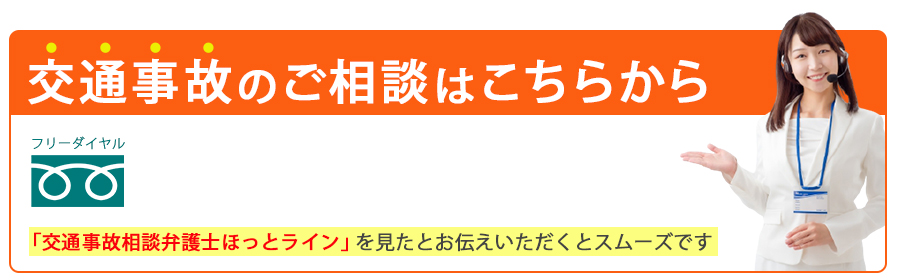
-
登録カテゴリや関連都市:
- 東京都


